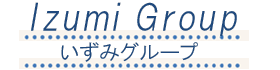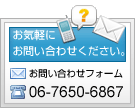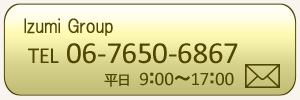相続・離婚
司法書士より

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
- (1)相続人の範囲
-
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位
- 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。 - 第2順位
- 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 - 第3位
- 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。 - (2)法定相続分
-
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2子供(2人以上のときは全員で)1/2ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。司法書士 植田冨和
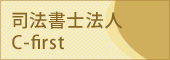
税理士より

相続税の計算のしくみは、つぎのように3段階になっています。
第1段階 課税価格の計算
第2段階 相続税総額の計算
第3段階 各人の相続税額の計算
まず第1段階では、相続財産の価格を計算します。相続税の対象にならない財産(非課税財産)や相続財産から差し引ける被相続人の債務もここで控除します。
第2段階では、第1段階で計算した課税価格から基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数)をマイナスして課税遺産総額を計算し、法定相続通り相続したと仮定して相続税の総額を計算します。
第3段階では、実際に相続した人が相続した財産の割合により相続税額を計算するのです。
このように相続税の計算は非常に複雑ですので、期限内(死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)に申告するためにも、専門家に相談されることをお勧めします。
また、実際に相続が起きる前に、専門家に相談することによって、相続税の節税や納税資金の対策も可能になります。
税理士 岡本望